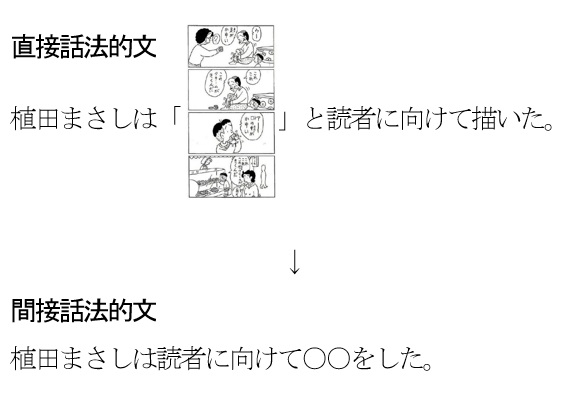
二度目以降のアクセスの場合、リロードを推奨します。参考:ホームページを更新したのに「内容が変わっていない!」を解消するスーパーリロードとは
日本の学歴社会の重要な特徴の一つに「二段階選抜」という事項が挙げられるだろう。たとえば国立大学は長いこと、「一次試験で受験生を絞り込み、二次試験で学力を本格的に検査し選別する」という二段階選抜を行なってきた。だが、このような表向きの二段階制にとどまらず、実質的にもさまざまな次元での「二段階選抜方式」は散見される。たとえば、時代が就職氷河期に移行する頃から、「一次試験で(志願者には知らせないであらかじめ)高偏差値大学の学生に志願者を絞り込んでおいて、二次試験(受験者からすると一次試験)でコミュニケーション能力や積極性を検査し選別する」といった方式で大企業は入社志望者を選択してきた。その結果として、たとえば「学力を向上させるための勉学で必死のあまり、コミュニケーション能力や対人積極性が未発達のまま来てしまった者」が割を食って失職したり精神を病むなどの「被害」も出たりもした。また、こういう企業の代表者などが「知識だけ在ってもダメ。コミュニケーション能力や積極性も無いとわが社ではやっていけません」というふうに述べるのを、自身が高卒である保護者が聞いて「そうよね、学力だけ在ってもダメで、やっぱり人間性も大事」と共感して子育てするときにも「被害」が生じている、と言える。というのも、大企業は「学力も大事かつ人間性も大事」も実質的には捉えているのに対して、この高卒の保護者は「学力<人間性」というふうに不等号的に捉えていて、そのような姿勢で子育てをすること間違い無しだからだ。つまり学歴取得をめぐる競争からわざわざ自発的に「降りて」くれること間違い無しだからだ。
これ以外にも「二段階選抜」によって一定の影響を蒙ってきていた側面が在る、と言いたいのだ。以下二つの側面について述べる。
日本の学歴社会の、比較的隠れた二段階選抜の方式に「日本語での授業は音声の聴き取りで行なうことがわかっているのに、入学試験での日本語力のチェックは文字の読み取りで行なう」というものが在る。授業では「聴き取り」能力が重要なのに、その音声での授業についていけるかどうかを検査するためと称して行なう入学試験のほうは文字の「読み」で検査する、というわけだ。これはれっきとした二段階選抜である。ここで割りを食うのが「文字の読解は得意だが、音声の聴解は不得手」という者だ。
ここで事実を直視するなら、「文字の読解はできるが音声の聴解は不得手という生徒・学生」が居る、というふうに捉えるのと同じくらいに「文字での執筆はできるが音声での講義は不得手(自覚無し)という教師」が居る、というふうにも捉えたほうが良い。つまり「音声での講義がちゃんと聴き取られない」というときに、その責任が聴き取る側に属するのか、それとも話す側に属するのか、は判定が難しいはずのものだ。しかし実際にはその結果(成績が悪いなど)を引き受けさせられるのは聴き取る側のほうなのである。そして、音声の聴解が不得手のため不成績である者は、単に蔑視されたり、或いは別の原因によるものだと誤解されたりして、今まで処理されてきたことが多いだろう。
この件の背景に在る「音声講義の聴解」に影響しうる日本語の問題・或いは音声言語一般の問題に関しては、主に「見逃されてきた日本語の「聴解力」、特に「音声同定力」の背景に在る問題」を参照して欲しい。
ともかく、入学試験は文字列の読み取りだけで行なわれるにもかかわらず、それで選抜された者には、「音声→文字」の変換能力こそが入学後の授業で常に要求されることになる。このような二段階選抜を行なっていることが、日本の学歴社会の裏の大きな一面なのである。
そしてこのような、比較的隠れた二段階選抜は、いっけん全然異なる問題と「同じ形」をした問題であると言ってよいのだ。それは「大学生や小学生がちゃんとした文章を書けない」問題である。これもまた別種の二段階選抜の一側面なのだ。そのことを次に述べる。
今しがた述べたように、「文字を読み取る」ことよりも「音声を聴き取る」ことのほうが日本語に限って言えば、明らかに高度なスキルである。欧米語なら、音声での講義を聴き取ることのできる者が、文字で書かれた同内容の文章を読めるとは限らない。文字が読めないだけで音声でのやり取りはできるという者が必ず一定数居るからだ。だが、その事態は日本語では成立しない。だから日本語の講義を聴き取ることの充分できるという者は、文字で書かれた同内容の文章はより容易に読み取ることが必ずできるのである。だが、これは「聴き取り」や「読み取り」といった「受信型」の能力に関してである。そうではない「発信型」の能力である「話す能力」や「書く能力」に関しては、同じ関係が成立するとは、決して言い切れない。それどころかそこには、別の種類の「二段階選抜」が成立する余地が在るのだ。ただそのような見方は通常されない。まずその点を述べる。
レポートや試験での文章の書き方というのは、マナーや形式・格式に小うるさいと思って良いだろう。書店に行けば大学生用の「レポートや論文の書き方」本がたくさん売っているのも、一つにはそれが「まずマナーや格式にうるさい」課題だからである。何よりもまず学術論文がマナーや形式・格式におおむねうるさいのであり、そのことがレポート課題にも波及しているのだ。そしてその「マナーにうるさい」という点がさらに、大学生の課題だけでなく、入学試験での答案の書き方にまで及んできていて、それも在って、高校生以下の学齢にある者ですらも従うべき規範になりうるわけだ。
レポートや試験答案などの書き方の一大特徴というのは、「もし他の要素を付け加えること無く、それだけを全文、音声で人前で発音し続ける者が居たならば、他の者には異常者や不審者としか受け取ることができない。そのくらいに異様な聞こえ方になる」というものだ。つまり、「レポートの書き方というルールに忠実に従った文章」がそのままの形で音声化されて身近で見聞される、ということはまず絶対に無い。
レポートや試験の答案で用いることのできる文体は、「そのままの形の音声」としては周囲に存在していない。つまり、「音声での講義」をしっかり聴いたとしても、その聴覚体験をそっくり再現するような形で試験やレポートといった課題を遂行することはできない。そこでは、「レポートや試験で許容される文体」への変換が求められるのである。つまり「音声での日本語文体表現→文字での日本語文体表現」の変換である。
とは言え、この変換能力をそのまま「二段階選抜」の二段階目と呼び、かつ、位置づけることには賛意があまり得られないだろう。というのは、「音声の講義」で使われているような文体と「レポートや答案」で使うことが望まれる文体とでは、そこまでかけ離れているわけではまったくないからだ。つまりこういうことだ。音声での日本語というのは、喩えて言えば「絵画を額縁に収めたもの」というのに近い、その一方でレポートや答案で用いることが要求されている日本語というのは「額縁なしの絵画だけが転がっているもの」に近い、…と、そのように思えるわけだ。要するにこの例でいう「額縁」に匹敵するような言語的要素を除去さえすれば、音声での講義を「お手本」として、その聴覚体験を基にしてレポートや試験答案を書くことも可能だろう、その除去操作はそんなに難事でもあるまい、と漠然と信じている人が多いのだ。もちろん、実際には音声の講義では文体面ではなく文法面を見ていけば、「助詞無し」「述語無し(体言止め)」「ねじれ文」などが発話されることもけっこう多いのだから、「除去」だけで事が済むケースは多くないに違いない。だがその状況は看過されてもいるだろうし、「講義の日本語がどこまで文法的に不完全か」という検証がされているわけではない。いずれにせよこれらから次の事が言える。
それは「レポートや答案」で使うことが望まれる文体というのは、積極的に存在する在り方ではない、と言ったほうが良い、ということだ。つまり「望まれる文体」というのは「レポートや答案で使うことのできない文体」を頻発しているケースを除外したり、「レポートや答案で使うことのできない文体」の特徴をそぎ落としていくことで得られる、消極的にしか規定できない存在である。言わば「最大公約数的な言語形態」に近いものなのだ。だから「文字列を音声に置き換えたもの」は現実に周囲に存在しないと言ったが、それは言わば「額縁抜きで転がっている絵画」が存在していない、という意味であって、「絵画抜きの額縁」ばかりが周囲に存在している、という意味でではない。「文字で書かれた日本語文書」の中からどれか任意の一文を抜き出して、それと同等の音声が存在していないか、と言えばそんなことは無いのだ。ただ音声の形で現実に存在しているときは、そこには何らかの「額縁」すなわち、音声の形で存在しているときに特有の文体や文章が必ず付随・補足されるに違いない、ということなのだ。
論文・レポート・筆記試験の答案で用いることを要求されている文体に関して、「それはマナーやルールの次元の問題である」と捉えている人は多いと思う。実際、それを「従うべきルールや、配慮すべきマナー」として述べている大学生向けの書籍は少なくない。この立場の者にとっては、ここには「二段階選抜」は存在しない。単なるマナーやルールの問題なのだから、守ることも破ることも能力的には可能なのだ。だからつまり、大学での講義を理解しあるいは咀嚼できているかどうかの評価のために、文字での筆記試験やレポートを行なうことは問題視されない。音声で聞き取って理解できることと、文字でその成果を表現することとは、別の事柄とは見なされていないのである。というのも、音声で聞き取ったものから、「音声での言語に固有の要素」をそぎ落としてさえいけば、おおむね良いからだ。そこに高度な能力など要らない、というわけだ。
そのタイプの考えに該当しそうな事例をたまたま一つ見つけたので、以下に引用して示しておく。石原千秋『大学生の論文執筆法』(2006,筑摩書房)(amazon)のp36「話し言葉と書き言葉は違う」より。マナーやルールやそれに近い語彙は一切使っていないが、しかし実質的にはこれはマナーやルールとして述べているのだと私は解する。
レポートに「やっぱ」とか「いまいち」などと書く学生が多い。そういう学生には話し言葉と書き言葉は違うものだと教えなければならない。言文一致などというから誤解する学生もいるが、話すように書いたら読みにくい。大学のレポートでは、「やっぱり」ではなく「やはり」、「いまいち」ではなく「いまひとつ」、「ぶっちゃけ」ではなく「率直に言えば」などと書かなければならない。
ただし、この本は「論文執筆法という論文」ではなく「論文執筆法という単なる書籍」なので、この本自身は論文やレポートのルールやマナーを守る必要は無い。なので、次のような話すように書いた
箇所も平気で存在する。p55。
ちょっと待って!「はるかに高いことが分かった」という大雑把な結論を出すために、「両方ない人の危険度を一とし」てみたわけ?たしかにその後に何倍危険かが示してあるから、「一とした」こと自体はおかしくないのだが、この文章はおかしい。これは「両方ない人の危険度よりも、食道がんになる危険度がはるかに高いことが分かった」とでもあるべきものだろう。
こんな古いものまで取ってあるなんて、僕は性格が悪いなぁ。それに、ずいぶん熱心に新聞を読んでいるものだ。自分でも感心するほかない。
「論文執筆法という本」でも、またおそらく石原の実際の音声での講義でも、「レポートや論文や答案でのルールやマナー」の見本がきっちりと体現されてはいないわけだが、でもそれでいいのだ、ということになる。というのも、こういう本を読む者も、石原の講義を受講する者も、言わば「能力」の点で問題を抱えている者は居ないからである。だから石原の受講生のうちレポートのマナーが守られていない者というのは、単に従いたくないから従っていないのに過ぎないのであり、「能力の問題」ではないのだ。…と、そのように言えるだろう。
ところが、それとは別に、論文・レポート・筆記試験の答案で用いることを要求されている文体に関して、それを「マナーやルールの問題」とシンプルに捉えていない人も居る。その場合、「能力の問題」と捉えられているようである。そこでは「レポートや筆記試験の答案を、音声を話すように書いてしまう能力の低い者」という見方が存在する。戸田山和久や石原千秋の「論文の書き方」関連書籍では問題設定の中心をあまり占めていない見方である。
次の論文「短大生の記述力に関する考察」ではそれを「能力の問題」と捉えていると明示されていないし、この著者古田自身はそうではないかもしれない。だがこの論文を読んだ者の中になら、「能力の問題」と見なす者が出てくるだろう。というのは、この論文の表5「年度別の“被服学”答案に見られる誤り例」の中には、「能力の問題」とあきらかに思える「漢字の誤りや不使用」というケースと同列・並列になるように「話しことばの使用例」という項目も列挙されているからである。つまり「音声を話すようにレポートや答案を書いてしまう」ことは「漢字を間違えたりひらがなばかりで書いてしまう」ことと「同列」「同根」であるかもしれない、というわけだ。古田貴美子 「短大生の記述力に関する考察 -「被服学」の試験答案にみられる変化-」)。
ここで或る種の人が想定しがちな「能力の問題」というのは主に「堅い本や文字のメディアを読んだ経験から来る能力」のことだろう。「堅い本」の中には、レポートや答案で使うことが許されていない「話すようなときの言葉遣い」も無論登場しうるが、同時にレポートや答案で使うことが推奨されているような「儀礼的な文字文章での言葉遣い」もまた登場しうるからである。だから「堅い本や文字のメディア」に接している度合いが高い者になら、両方に接しているのだから文体の選択は自由自在である。それに対して、「堅い本や文字のメディア」に接している度合いが低く、同年代の者と音声での会話ばかりしている者は、「文体の切り替え」をするだけの文字経験が少ないため、その能力が低い、…というわけだ。そして、「文体の切り替え能力」の低さと「漢字を書く能力」の低さとが、同時に発現しているのだ、…というわけだ。
とは言え、この被服学の調査結果は、そうひどい状態のように私には思われない。この短大の学生は、授業を聴きとって書き取ることもできそうだし、内容の理解もそう悪くなさそうに思えるのだ。たとえば「紫外線」を「紫外綿」と答案に書くような学生ならば、授業で「しがいせん」という単語を聞き取ることもできそうだし、内容も理解できそうだ。ただ単に、書きとらせてみた場合漢字を間違えていただけだったに過ぎないのだ。この学生なら、「堅い本」で「紫外線」と正しく表記されていても読み間違えることも無かろう。そのように見えるのである。他の例も同様にそう深刻なものが多いとは思われない。少なくとも自分が専攻している分野の音声や文字なら受信できるだろうと思わせる(ただし他分野や新聞だとどうなるかはわからない)。この調査から浮かび上がってくる学生像から想像できる問題点というのは、漢字を習得するときに手指を使って鉛筆などでの習得はあまりしていなさそうだ、というものでしかない。これは重要な問題だとは思うが、本件とは別に検討するべきだろう。ただ、これらの学生には同世代との会話を好む学生が多いために、そしてそれを相殺するほどには「堅い本」を読む習慣も無いため、答案に「話しことば」と見なされるものが時に混入することも在るというのにすぎない。「堅い本を読む習慣の少なさ」という点では共通した要因をもつことになるため、「誤字」も「話しことばの混入」も同列に扱われるというわけだ。大学教員からすれば結局は「堅い本を読んでいる度合いが少ない」という点で、漢字の誤字も話しことばも「能力の問題」とも扱いうる。
上記のようなケースを、「大学の授業で小学校範囲の内容の復習を行なう」ような大学でのそれと混同してはいけない。確かにこの場合も、おそらく書かせてみれば誤字も多く、そして「話しことばの混入」も答案やレポートに散見されることになろう。誤字というのも、「理にかなった誤り」とはかけ離れたものが増加もするだろう。たとえば、「“自画自賛”を“自我自賛”と書くのは理にかなった誤りの部類である」とする。だがそうではないこのレベルの学生の場合、そもそも講義を聴きとれない、誤字でもいいので漢字で書き起こすこともできない、…ことが充分に想定可能である。講義を文字で起こしても学生にその漢字が読めないものだらけになるのである。教員のほうが学生に相当に歩み寄る気が無ければ、きっとそうなる。たとえば、かりに高偏差値の大学で、「“デカルトの会議”ってなんだろう?わかんないけど、まあいいや」「今まで“自我自賛”だとばっかり思っていた!」という学生がまあ居たとしよう。これを数倍グレードアップしたようなレベルでの「聞き取りや内容理解の誤り」「理にかなった誤りからかけ離れた誤り」が、この種の大学と学生の間では起こりうるのだ。これは先の被服学の学生や学校でのものとは、まったく異なった話である。このレベルの学生が先の被服学の講義に出席したところで、聞き取った内容が同定もできず、理解も当然できないため、退学することになるほどの理解状況になるはずだろう。ただ、この種の学生は、漢字語を多用したテレビの幼児番組から小中校の授業に至るまで、「音声を聞き取って理解する」ことが穴だらけであることに慣れている。その穴だらけの状態が当然だと思って育っているわけだ。だから、実際に退学してしまうことはあまり無いだろう。ともかく、この場合であっても「堅い本を読まないから、漢字も書けないし、レポートに話しことばが混入してしまう」状態に帰結するだろう点では同じなのだ。だが、さきの被服学の学生とはレベルが違いすぎる。共通点にだけ目をとらわれないようにしたいところだ。
ともあれいずれの場合であっても、「独演的な文字言語に接した経験値の不足」と「双方向的な音声言語に接した経験値の過剰」とが一人の人物に同時に起こる、という点で共通しており、これが「話しことばの混入」を「モラルの問題ではなく能力の問題である」と位置づけさせることになっているのである。
その結果として、ここで「二段階選抜」が起こりやすい。たとえば、石黒圭『論文・レポートの基本』(2012,日本実業出版社)では「第10課 話し言葉と書き言葉」のなかでの「表12 論文では避けたい話し言葉の例」や、「第11課 論文になじまない言葉」などといったコンテンツが主張されている。この内容だけでも、こと細かい校則というものが印象として与えるくらいには私はうんざりさせられる。だが、著者の石黒に文句を言ってもしかたがないだろう。石黒と似たような基準で、多くの、大学その他の教員が、論文やレポートや試験の答案を審査し採点しているかも知れないからだ。そして、それは石黒個人や石黒の属する学会の問題だけではないかも知れないからだ。のみならず、このような基準を「こと細かい校則に類似したもの」としてではなく「当然の基準」として捉えているかも知れないからだ。そういうわけで、この種の「論文では避けたい」語句や言い回しや表現といったものリストを見たことが無い者は、音声の講義を聴くことしかしていないため、そして音声での講義は推奨されるような表現の手本にはあまりならないため、レポートや試験答案で良い点がもらえない、ということになりやすいわけだ。またそれを「文字のメディアに接している経験値の不足」(という能力の問題)として扱いたければ、その経験値の不足のため「文体や語り口の切り替え能力が不足した」という把握の仕方になろう。あるいは、「放っておくと、つい、若者言葉になってしまう」というのも一種の「能力の不足」だとも言える。
この二段階選抜は、「音声での講義では、講義を“内容”と“語り口”とに分断して理解して、そのうち“内容”だけを踏まえて答案やレポート課題に取り組む、その際、日常生活で経験している“会話等での語り口”が混入しないようにする」というものになっている。すなわち、授業を理解したりそれを踏まえた考察や議論がただできれば良い、というものではないぞ、と、そこに「日常会話等の語り口」が混入しないように注意しなければならないぞ、というわけだ。
レポートや答案の日本語に、「会話等での語り口」が混入してしまうのが、「マナーの問題」であると認識されて、「能力の問題」であるというふうにあまり認識されないわけは、こうだ。それは、大学生のレポートを採点評価する側の多数派というのは、「ふだんから学術的内容を日常的な会話の形・文体で話す相手が常時周囲に存在しており、その話すときの口調で耳にすることに慣れてしまっている」か、または「そもそも話し相手がほとんど居らず、その人物の聴覚体験としては大学での音声講義の内容というものが脳内に占めている割合が相対的に高いか」のいずれかなのである。いずれにせよ、そこには「論文のような内容からかけ離れた内容」を「同年代の者」と日常的に音声でやりとりしている営為が生活の圧倒的な中心になっている者への考慮や配慮は無い。そういう音声を大量に聞いてしまっているという体験が、大学教員の多数派には聴覚経験として乏しいため、その体験を遮断し忘却する「能力」が学生に必要になるなどとは思わないのだ。だから単なるマナーの問題だと理解される。ここに在る構造的な問題というのは、一つには「偏差値70以上の大学で教える教員」も「偏差値40の大学で教える教員」もどちらも出身校はだいたい「偏差値70前後大学の出身」である、ということに起因するものでもあろう。偏差値がそこまで影響が大きいかはわからないが、少なくとも漢字力には関係するだろう。その「漢字力」にも、「講義の内容を文字で読み同定し意味理解をすることならできるが、書く段になると誤字を書いてしまう」レベルから「講義の内容を文字で読むことすら困難である」レベルまで、相応に幅が在る。しかし、大学の教員のなかでも学生に歩み寄る気や能力に大いに欠けている者であれば、その漢字力は「どっちもどっちでしかない」となるだろう。
「レポートを話しことばで書いてしまう」という用法に限らず、或る程度広範に使われる「話しことば」と「書きことば」という語の用法の間には、非対称を指摘する以前に、まず複数の用法が混乱の種をはらみつつ並立している事態をまず確認する必要がある。その点については、筆者の書いた「問題の所在:「“書き言葉”という単語」を使いたがる人」を参照されたい。その点を認識してもらったうえで、「レポートを話しことばで書いてしまう、きちんとした書きことばで書くべし」というときの「話しことば」「書きことば」には非対称が在ることをさらに確認しておきたい。
二種類の非対称のうち、一つめはこうだ。「レポートを話しことばで書いてしまう」という「非難」は言説としてしばしば見聞するのに対して、「講義を書きことばで話してしまう」という「非難」はまったく見聞することが無い、これである。たとえば私が何度も書いていることから自然に導出されるように、講義・授業で話す教師が、抑揚も同じである同音異義語を連発したら分かりにくくなるから、ぜひ使用を控えた方が良い、と教訓化することは、可能である。にもかかわらずその教訓化の場合であっても「講義を書きことばで話してしまうのは全く良くない」という言い方はまず絶対にしないのだ。もししたとしても、それは単独では理解されず、補足説明を要する主張になる。同様に、講義や会話で難しい漢字語や、文語調の古い言い方を用いる者に対しても、「講義や会話を書きことばで話してしまう」という非難はまずしない。そうではなく「難しい単語を使う」とか「時代錯誤の言い方をする」などというように、別の語を用いて非難することが多いはずだ。おそらくその理由は「書きことば」というのが、私の造語で言えば半側評価語であり、「どちらかと言えばほめ言葉」「少なくともけなす言葉ではない」というふうに、限定された使い方しかされない語だからだ。無論「話しことば」はちょうどその真逆なのである。つまり「少なくともほめ言葉ではない」のである。だから、「この小説では登場人物の話しことばが生き生きと書かれている」という賞賛するような言い方も、たぶん、通常はしない。ほめる場合には、何か別の言い方でするだろう。
二種類の非対称のうち、二つめはこうだ。それはそもそも「話しことば」と「書きことば」というのが、特定のタイプの「話す」や「書く」に限定されており、きちんとした対称形になっていないことだ。次の表を見ていただきたい。
| 「話しことば」 | 「書きことば」 | |
|---|---|---|
| 使用媒体 | 音声 | 文字 |
| 対面性 | 対面的。聴覚のみ対面的(電話)も可。 | 非対面的 |
| 送り手の交代 | 送り手の交代が不定期に起こる | 送り手の交代は起こらない。独演。 |
| 方向 | 双方向的 | 一方通行の独演 |
このような表にしてみればいかに体系的にものを考えていない国語教師であっても、「話しことば」と「書きことば」とが対称的にできている二項対立だとは思わないであろう。次の表の存在がすぐに思い浮かぶからである。ただし、ここでわかりやすさよりスマホでの見やすさの方を重視して表の縦横を入れ替える。
| 使用媒体 | 対面性 | 送り手の交代 | 方向 | |
|---|---|---|---|---|
| 三人以上でのお店での歓談 | 音声・身振り | 対面 | 送り手の交代が不定期にありうる | 双方向 |
| 電話での対話 | 音声 | 視覚では非対面 | 送り手の交代が不定期にありうる | 双方向 |
| テレビ電話での対話 | 音声・身振り | 対面 | 送り手の交代が不定期にありうる | 双方向 |
| 司会者によって統御された会議 | 音声・身振り(・補助で文字) | 対面 | 独演 | 双方向 |
| 音声での講義 | 音声・身振り(・補助で文字) | 対面 | 独演 | 一方通行 |
| テレビでの(一人での)報道 | 音声 | 送り手側は非対面 | 独演 | 一方通行 |
| 電子メールでのやりとり | 文字 | 非対面 | 予期せぬ送り手の交代はない | 一方通行もありうる |
| 電子媒体でのチャット | 文字 | 視覚では非対面 | 送り手の交代が不定期にありうる | 双方向 |
| 隣席どうしの授業中の生徒の筆談 | 文字 | 不完全な対面 | 送り手の交代が不定期にありうる | 双方向 |
| 交換日記・定期的な文通 | 文字 | 非対面 | 独演 | 双方向(一方通行もありうる) |
| レポートや筆記試験での内容 | 文字 | 非対面 | 独演 | 一方通行(返却・添削はありうる) |
要するに、「実際に話された言葉/実際に書かれた言葉」とを比較する場合には、変数のさまざまな組み合わせがあり単純化はできにくいはずなのに、言説上の「話しことば/書きことば」の比較では「対面双方向状況での話者の交代が起こりうる対等な相手どうしでの音声会話での発話/レポートや論文や答案での独演的な文字の文章」という恣意的な比較をしているだけなのだ。従って「レポートや答案を話しことばで書いてしまう」というときの「話し」ことばというのは、「大学教員の音声での講義のような」ということでは、ほぼない。そうではなく、「双方向的で話者の交代も在りうるような若者どうしでの会話」のようなものが積極的に想定されている。「目上の者に提出する独演的な文字での文書であるのに、同世代との双方向的で送り手の交代も起こりうるときのような音声上での若者言葉まじりなんかで書いている」ということなのだ。
一つ簡単なチェック項目がある。レポートや答案に顔文字を記述してきた学生が居たという場合である。顔文字は音声的な存在ではなく、文字的な存在である。したがって、「書きことば」に入ることは在っても、「話しことば」のほうに入ることは無さそうだ。だが、そういうレポートであっても「レポートを話しことばで書いてしまう学生が居る」と言いたくなるかどうか、である。もしそこで言いたくなる者が多いのなら、その「話しことば」の「話す」というのは「音声/文字」の区分に対応したものではないことになる。おそらくそれは「送り手の交代がむやみに起こらない(独演)/送り手の交代が不定期に起こる」という区分か、または「双方向/一方通行」という区分のいずれかに対応しているのである。そして、それは「携帯」でも「筆談」でも使用可能な言語要素である。なので、顔文字を「話しことば」に入れたいという者は、その「話す」ということで区別している特徴は少なくとも「音声/文字」という水準には無いのだ。私自身は、そのような立場の者がもし居るのなら、それを「話しことば」とは呼ばないべきだ、と感じる。
なお、この節の内容と関係しているものとして「00年代の国語力革命は評価語ばかりのずさんな掛け声で動いていた。」が在る。
日本の学歴社会は、かなり目立たない部分として二種類の二段階選抜を行なってきた。一つは「授業は音声の聴き取りで行なうのに、その受講できる者の選抜は文字の読み取りで行なう」というものであった。そのため「文字の読み取りは得意なほうだが、音声の聴き取りは不得意だ」という者が、二段階目で低い評価をもらい、敗者となる。もう一つは「授業は音声で話されるのに、その聴き取りを前提とした成果評価は文字を書く課題によって行なう」というものであった。ここでは音声での講義はいわば「額縁に入った絵画」のようなものであり、文字の課題は「額縁から取り出した絵画」のようなものなので、いっけん二段階選抜のようには見えない。だが、その「文字を書く課題」において「別種の状況での音声コミュニケーションの言語要素」が混入してしまい、それを手際よく除去できない者が居る。主に「文字のメディアに接している度合いの低い者」である場合が多いだろうと推測できる。ともかくそのため、そのような者が二段階目で低い評価をもらうことになる。
後者の二段階選抜をそのように捉えないで「レポートや答案を話しことばで書いてしまう」というふうに捉えると、ここには概念の非対称があるため、日本社会の二段階選抜を見落とすことにもなる。一つは「音声の講義を書きことばで話してしまう」教師の存在による二段階選抜を見落とすことになる。もう一つは「レポートや答案に書く日本語(彼等の言う“書きことば”)そのままの形では講義はできない(そのまま話すと異常者になる)」ことによって、音声での講義をただ単に受講しているだけでは、文字での課題のお手本にはならないこと、つまり授業以外の時間に文字のメディアに接して、ある程度多様な文体を使い分けられるスキルを獲得することが暗に求められるが、そのことが見落とされる。
また文体の問題とは別に、音声の講義や授業で実際には或る程度多く見られるはずの「助詞無し」「述語無し(体言止め)」「ねじれ文」「倒置文」などの発話に関しては、それを受講している者がしなくてはならない「作業」は「音声発話に特有の語要素の除去」だけではなくなる。「文法的に必要な付加」もまた要請される。この点に関しては重複内容も多いが「授業なんかに出ているから<国語力>がつかないのだ」にも関係した内容を記載している。この面もまた「二段階選抜」の一翼を担っている場合が少なくないであろう。
「コボちゃん作文」をはじめとする「マンガ作文」に仕方なしにつきあってきた子供たちも、今では成人してけっこう経っている者がかなり多くなっている。そのなかに、コボちゃん作文によって文章を書くことが嫌いになった、という二重に良くない影響を蒙ったかたがたもじゅうぶん多いはずだと推測される。そのかたがたを想定して、次の補論を書くことにする。コボちゃん作文はそれを言いだした人間がきっちり考えを詰めていないからそういうことになったのである。以下それを述べる。
「マンガ作文」では「“勝手にしなさい”とお母さんは言った。」のような書き方は良くない、と教えられる。つまり、せりふの内容を直接話法で書くことは嫌われる。そこで「間接話法で書きなさい」などと言われて、どうして良いのかも、なぜそんなことをしなければならないのかも、わからなかった人も居たことだろう。ともあれ確かなことは、コボちゃん作文は「そんなこと」をさせるために行なわれていたということだ。何のためかと言えば、「そんなこと」ができないようでは「前提となる能力が欠如している」と見なされるような世界が存在するからだ。
私は長いこと、その理由を「与えられたものを“そのまま”書くのではなくて、“自分のことば”で書く、という能力」をつけるため、だとこの主唱者が錯覚していたからだろう、と思っていた。つまり「勝手にしなさい」というせりふが通常「好きなことを必ずしろ」という「命令」ではなくて、「見捨てる」ときの「捨てぜりふ」である、とわかる「能力」をつけさせたいからだ、と思っていた。そして、その「能力」が「作文の初歩」のレベルだと考えるのは思いあがった大人の「錯覚」だ、と思っていた。でも、おおもとの理由はたぶんそれとは違う。事態は全然それ以前だった疑いが濃厚である。
書くことは「自分」を創りあげること(工藤順一インタビュー)を参照してみる。
(前略)最初のうちは、ふきだしの言葉そのままを書いてしまう子が多くて大変ですよ。それをだんだんに間接話法、「書き言葉」に変換させていくわけです。
(前略)しゃべり言葉でそのまま書いてしまう子、形容詞や形容動詞を適切かつ豊かにつかえない子も非常に多いですよ。
ふきだしの言葉をそのまま書くのが気に入らない理由は実は、「見たまま」を書いたから、ではたぶんない。この工藤順一という人物は、「しゃべり言葉」で書いたものは「自分の頭で考えた内容」であろうとなんだろうと、たぶんダメなのだ。ただし、これだけなら工藤に賛成する教育者も、或る程度居ることだろう。だが、実際はそんな生易しいものではない。普通の用法のうち半分強の場合は、「しゃべり言葉」というのは、「しゃべる時に使うような語要素」のことを指す。だが、工藤に限って言えば、そうではない。
これは、正しい書き言葉で文章を書くということが学校では全く教えられていないことも一因です。話し言葉と書き言葉は語彙が違うだけではなく、考え方そのものが違うんですね。(後略)
書くことは、目の前にいない人、情報を共有しない多くの人に、自分が現実をどのようにとらえ、何を考えているかを伝えるための一つの「手段」であり、「道具」なのです。
(前略)最初のうちは、ふきだしの言葉そのままを書いてしまう子が多くて大変ですよ。それをだんだんに間接話法、「書き言葉」に変換させていくわけです。
工藤はここで「“ふきだしの言葉そのまま”というのは“変換”するまでは“書き言葉”なんかではない」と同種の事柄を述べている。つまり、マンガの作者のたとえば植田まさしは読者に対して、「書き言葉ではないような“ふきだしの言葉”」というものを読み物として提示している、と述べていることになる。工藤という人物が「書き言葉ではない」と述べるというのは(他の人物が述べる場合と異なり)、すなわち「状況を共有していない他者には伝わらないものである」と述べていることになる。マンガの作者の植田まさしは、少なくともふきだしの言葉の箇所は、状況を共有しない他者には通じないようなそんなもので埋めてしまっている、と言っているにも等しいわけだ。ずいぶんと失礼な言い草だが、まあ工藤というのは私が今提示したような、そんな受け取りの可能性を考慮もしない人物であるわけだ。
もちろん「ふきだしの言葉」や「間接話法、“書き言葉”」と言っているときの「言葉」というのは「単語・語句・文体を構成する語要素」を指すのに対して、「話し言葉と書き言葉は語彙が違うだけではなく、考え方そのものが違うんです」というときの「言葉」は「言語活動」を指すのだろうし、だから「大は小を兼ねる」ので「言語活動」という用法の場合も「単語レベル」の用法を含むこともできる、という状況なのだが、工藤という人物はそのようにして他人に説明することのできない者なのである。だから「マンガ家植田まさしの読者に対してなした言語活動(工藤のいう書き言葉)」を指して「そのなかの語要素」のことを「書き言葉に変換しなければ通用しないもの」として扱うこともできてしまうし、そんな(マンガ家に対して失礼な)受け取りの可能性など一度も考えたことも無いという自己検証すらしていない人物なのであった。
ともあれここでの今一つの教訓はこうだろう。前述(「問題の所在:「“書き言葉”という単語」を使いたがる人」を参照先に指定した)したように「話しことば」とか「書きことば」という単語は、複数の用法が混乱の可能性をもちつつ並立しており、その事があまり世間で意識されていない。なのでそこに乗じて「言葉のトリック」を弄することも可能であり、その一つの帰結が工藤の根拠不明の、特に「書き言葉」という語の(一貫することが不可能な)用法なのである。その際に、工藤の一番いけないのは、「読者に断りを入れる」必要性を毫も感じていないかのようなこの表現態度である。読者は「なぜそれをことさらに“書き言葉”と呼ぶのか」と思っているのに、その説明をしないわけだ。そのような教訓こそを感じ取ってほしい。たとえばこうだ。
工藤の著書『文書術―読みこなし、書きこなす』(中央公論新社、2010)に在る次のような箇所だけみても、この人物の用語法が破綻していること、にもかかわらずそれを読者に説明する気が無いことが、推察できるのだ。p11。もちろん、この本を買ったりなどしなくて良い。
まずは、「書き言葉」「話し言葉」という言い回しの中にある、「書く」「話す」という意味にしばられてはいけません。「話し言葉」を小説などでも見かけるように、「書き言葉」で話す場面もあります。(後略)
「では、にもかかわらず“書き言葉”“話し言葉”という呼び方を私がなぜ採用するのか、その理由を説明しよう」という展開をその後しないのである。また、工藤は「話し言葉」の存立根拠を「視覚的・対面的な状況の共有」において説明するので、固定電話や携帯電話でのやり取りすら、「話し言葉」に入れることができない。物理的に対面しているときの会話しか「話し言葉」の成立に関係しないわけだ。なので「なぜ、電話での会話すら含まれないようなものに限定して“話し言葉”とことさらに呼ぶのか、それを説明しよう」という展開がされないとおかしいのだが、もちろん工藤はそういった説明を一切しないのである。そこで「電話でも通用する」ような「状況の共有」ということを言い出してしまうと、「では、文字の出版物にもそれは当てはまりますね」となるからできないのだ。
この内容は、「00年代の国語力革命は評価語ばかりのずさんな掛け声で動いていた。」とも関連している。
で、ここで話を終えても良いのだが、これだけだと教材に使われてしまったマンガやその作者にあまりに気の毒なので、もう少しだけ掘り下げる。
工藤が「書き言葉」と連動させて「話し言葉」という語をも融通無碍というか恣意的に使うことができた理由は、そのまま「マンガ作文」そのものへの無理解にもつながっている。要するに彼は「人と人とが話す」という現象自体をよく理解していないのだ。だから「話し言葉」という語を自分勝手に使うこともでき、かつ、マンガ作文というものが生徒にやらせている事柄も理解していないのだ。
次の箇所あたりに、工藤の「マンガ作文の理解のしかた」が露呈している。
(前略)ただ「考える」ということに関していえば、『コボちゃん』はあまり考えなくても、絵をそのまま描写していけばそれなりの作文が書けてしまうんですね。(後略)
「コボちゃん作文」は「客観描写」の初歩的な手法ですが、漫画の中で「もの」や「ことがら」がどのように配置されているかをきちんと見分け、それをできるだけ客観的に正確に書くことを訓練します。(後略)
(前略)最初のうちは、ふきだしの言葉そのままを書いてしまう子が多くて大変ですよ。それをだんだんに間接話法、「書き言葉」に変換させていくわけです。
これらの箇所を記憶にとどめておけば、絵をそのまま描写していけば
という箇所とふきだしの言葉そのままを書いてしまう
という箇所とが、どういう関係をもつのだろうか、と不整合の気配に気づくこともできるだろう。気づくも何も、この作文を実際にやらされた生徒からすれば「それこそが肝腎な点だろう」としか思えないはずであるほどだ。そして漫画の中で「もの」や「ことがら」がどのように配置されているかをきちんと見分け
という箇所の中に「せりふ」が入っていないことにも気づくだろう。無論、工藤順一という人物は、マンガのなかに「せりふ」が「どのように配置されているか」を他人に説明できない人物なのである。
マンガのなかに限らないが「せりふ」や「人の発言」というものには、或る程度の秩序がきちんと存在する。「“勝手にしなさい”とお母さんは言った。」と書けば「ふきだしそのままを書いてしまう」と評価されてしまうかもしれないが、「“勝手にしなさい”とお母さんは息子に言った。」と書けばそれだけでも、マンガの「せりふ」の「漫画の中」での「配置」が少し明らかにされる。あるいは「“今日の晩ごはんはステーキ以外食べたくないな”と息子は母親に言った。」に後続する箇所なら「“勝手にしなさい”とお母さんは息子に答えた。」と書くこともできる。このように「せりふ」「発言」のうちどれが「応答」に該当するものなのか、を明確にすることもまた、マンガの「せりふ」というものが「漫画の中」で占める「配置」を明らかにすることに、つながる。こういうことがわかるようになると、生徒がもっと成長すればいずれ、マンガの吹き出しの中に「…」しか書いていない箇所であっても、「描写」することも可能になる。そこは「自分が発言することが自然・当然であるような箇所で沈黙している」ことを表すものだ、という「常識」が、わかるようになるからだ。
ただし、このくらいに「せりふ」の占める位置がわかっても、「勝手にしなさい」という発話が多くのケースで「命令」ではない、ということを知り理解することは難しい。また、これが「命令」でなければさて何なのだ、と尋ねられて「お前のことは助けない、見捨てるぞ、という一種の“宣言”である」といった回答をすることは、さらに難しい。ただこれらの点ができなくても、「勝手にしなさい」という発言をする人が「怒っている」ということは、目で見て絵に描いてある情報でだいたい「わかる」。…というか、その点が目で見てわかりやすいようなマンガしか、マンガ作文には向かない、と言えるくらいのものだろう。このタイプのマンガでは「登場人物の気持ち」が「絵に描いてある」のだ。マンガ作文が「苦行」にならないためには、その「絵に描いてある登場人物の気持ち」をベースに置いて書くしか、おそらく方策は無い。だが、それは工藤の意図ではないだろう。工藤は是が非でも「マンガのセリフを間接話法に置き換えた書き方をマスターさせる」ことを小学校低中学年の子供に行ないたいのだ。「そのためにやっている」のだ。つまり「話しことばから書きことばへ」というわけだ。しかし、これはたとえば体操の選手に「まずとにかく着地だけはきれいにやりなさい、簡単でしょ」とか、フィギュアスケートの選手に「まずとにかく転倒しないようにやりなさい、簡単でしょ」とか言って、その実最高難度の技を、その難易度の判断もつかない指導者がやらせているようなものであるのに近い。
マンガ作文では、たとえば「“勝手にしなさい”とお母さんは息子に言った。」と作文するのはまったくダメであり、そうではなく「お母さんは息子に、今後一切助けないし見捨てるという宣言をした。」というように作文しないと、ダメなのである。というのも、まさにそういう話法の形式を「習得」することが「能力」である、という価値序列に基づいているからだ。そしてその「形式」と対応している「内容」のほうの難易度、つまり、「言語行為の理解」の難易度はまったく考慮されない。この難易度が全くピンと来ていない読者がどのくらい居るのかはわからないが、そのような者には、次のように言いたい。間接話法での作文で要求されている、その理解の「難易度」というのは、次のようにすると判るのだ。
これと次の画像に記載した関係とは、形式的には同形である。
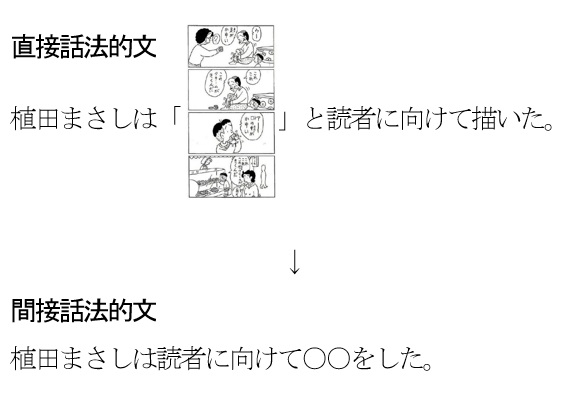
なお、画像に転載したマンガ画像は、小池康「―≪研究ノート≫―「国語」学力下位レベル学生の日本語作文における問題点」(PDFファイル)という、関東学園大学紀要Liberal Arts第21集(2013)に掲載された論文から、勝手に私が借用したものである。
さて、この画像に描いた変換をもし、きちんとした文字の文章で書くと、たとえば次のようになるだろう。(参考:拙稿「あらすじ・アブストラクト・要約」)
上掲の直接話法的文を間接話法的文に変換することは、マンガのセリフを間接話法で書くということで要求されている変換と、形式的に言えば同じことである。なので、その操作を遂行する「難易度」の見当をつける際にも少し参考になるだろう。上掲の「直接話法→間接話法」の変換が容易で初歩的な課題であると思える者なら、マンガのセリフを間接話法で書くことの内容的な難易度もやはり容易で初歩的な課題であると見なすことになるだろう。工藤自身はきっとそうだったのだろう。しかし、そうでない者も当然多いはずである。「マンガの中のセリフをそのまま書いてしまうから困る」などという理由で、その操作を課題として要求するなど、問題外である。
話を少し前の脈絡に戻す。
「勝手にしなさい」という発言のように、「文そのものの意味」と「その発言で言おうとしていること」とが異なっているように思える現象は、たとえば「言語行為論」という哲学や言語学の分野や、あるいはそれを使った社会学や文学の理論で研究されることがある。困ったことに工藤という人物は、『国語のできる子どもを育てる』とかいう書籍で、この「言語行為論」を「高校生のうちに学んだほうが良いでしょう」といった扱いで言及した。なので、この分野に詳しい人が読んだ場合、「さすが国語専科教室は、コボちゃん作文のような教育プログラムとして行なうにあたって、言語行為論まで参照しているのだな」と感心するように書かれている。そのためもきっとあって、この人物にあまりそれ以上の関心が知識人にはもたれなかった。だが、それはまったくの錯覚なのだ。工藤は「マンガ作文ができるようになること」と「言語行為論を学ぶこと」との間に関連が在るなどと考えたことなど、おそらく無いのだ。きっと言語行為論というものも、中身を知らずにただ格好をつけて書いてみただけ、というのが真相だろう。
「会話」という社会現象に大した理解をもたない人物がマンガ作文を考え出してしまったために、マンガの中の「会話」の扱いもぞんざいになったし、同時に「話し言葉で書かないため」にマンガ作文を行なうことがその意義だと述べるときの、その「話し」ことばという「話」すことの理解もいい加減になった。彼の言う「話しことばの特徴」は「電話」にもあまり当てはまらないし、講演や講義にも当てはまりにくい。一方で「電子メールでの文字のやり取り」に当てはまる点が無いではない。
そんなわけなので、「コボちゃん作文」がまだ残存していて行われている、と聞いて私は驚いた。もちろん巨視的にはすでに衰えているとは思うが、しかしこの手法がきちんとしたしかたで葬送されたわけでもない。だからいつまた幽霊のように現れないとも限らない。この文章がその葬送に寄与することを願う。
なお、この節の内容と重複しつつも別の指摘をもしている文章として「「慣用表現」の日本語力:コボちゃん作文の「指導者」に必要な認識」を公開している(特に最後の節「蛇足その2:コボちゃん作文の「指導者」に必要な認識」)。こちらの文章では、音声であるか文字であるかに関係なく成立する内容を中心に述べている。また「子供の語彙習得を俯瞰する」も関連が在る内容だ。併せて読むことを推奨する。